- 国内公表(買取価格1gあたり)
- 金 21,860円 (休場)
- プラチナ 8,711円 (休場)
- NY市場(終値ドル/トロイオンス)
- NY金 3,996.50ドル (-19.40)
- NYプラチナ ドル 1,575.40ドル (-38.90)
10/31、ニューヨーク市場の金は3日ぶり反落。始値4,038.20ドル、高値4,059.90ドル、安値3,982.30ドル、終値3,996.50ドル、前日比-19.40(-0.48%)。10月の米シカゴ購買部協会景気指数(PMI)が31日に発表され、前月の40.6から43.8へと上昇した。市場予想の42.3を上回り、予想外の改善を示した形となった。ただし、好不況の分かれ目とされる50を依然下回っており、製造業活動はなお縮小局面にあるとみられる。海外報道によると、今回の結果は「地域製造業の活動が予想以上に回復しつつある兆候」として市場関係者の注目を集めた。特に生産や新規受注の動きが持ち直しを見せたとされ、前月までの低迷が一服したとの見方が浮上している。一方で、雇用や在庫関連の指標は依然として弱く、持続的な回復を示すには慎重な見方が多い。米経済メディアは、「改善はしたが依然として縮小圏内にあり、製造業の根強い課題を反映している」と指摘。需要の伸び悩みや高金利環境が依然として企業活動の重荷になっていると分析している。また、予想を上回る結果となったことで、米ドル相場には一時的に上昇圧力がかかる場面も見られた。シカゴPMIは全米製造業の動向を先取りする地域指標として知られており、11月上旬に公表される全米供給管理協会(ISM)の製造業景況指数への影響も注目される。アナリストの間では「今回の改善が一時的か、底打ちの兆しなのかを見極めるには今後数カ月の動向が重要」との見方が多い。今回の結果は、米国の製造業が長期的な停滞から緩やかに回復へ向かう可能性を示す一方、依然として高金利や需要の不透明感に直面していることを浮き彫りにした。米連邦準備制度理事会(FRB)の金融政策を巡り、10月末の利下げ決定後も慎重論が相次いでいる。31日、米クリーブランド連銀のベス・ハマック総裁と、米ダラス連銀のローリー・ローガン総裁が相次いで発言し、いずれも「現時点での追加利下げには慎重であるべき」との見解を示した。海外メディアは、両総裁の発言がFRB内部での「ハト派」と「タカ派」の温度差を浮き彫りにしたと報じている。ハマック総裁は、「今回の会合では金利を据え置くべきだった」と述べ、利下げ決定に反対票を投じた理由を説明。「インフレ率は依然として目標の2%を上回り、政策金利は中立水準に近い。過度に緩和するのは時期尚早だ」と指摘した。米ウォール・ストリート・ジャーナルなどは、ハマック氏が「制限的な政策を維持する必要がある」と強調したと伝えている。一方、ローガン総裁も「今週の利下げは必要なかった」と述べ、「12月に追加利下げを行うには明確な経済的根拠が必要だ」と発言。労働市場がなお底堅く、コアインフレも高止まりしている状況では、急ぎすぎた緩和がリスクを伴うとの考えを示した。ロイター通信は、同氏が「金融環境を引き締めた効果が完全に現れていない」との認識を示したと報じた。市場では12月にも追加利下げが行われるとの観測があったが、両総裁の慎重姿勢を受けて、その見方はやや後退している。FRB内では依然として「景気下支え」と「インフレ抑制」のバランスを巡る議論が続いており、今後の指針は11月以降の雇用・物価データ次第となりそうだ。ニューヨーク・債券市場では米国債が買われ米長期金利が4.08%台まで低下し、利息や配当を生まない資産である金の強みとなった。外国為替市場でユーロは対ドルで下落。米追加利下げ観測の後退を背景にドル買い優勢となり、ドル建てで売買される金は割高感が高まった。本日の海外金相場は、1オンス当たり約4,011ドルで取引され、前日比でやや下落した。米ドル高と米連邦準備制度理事会(FRB)の利下げ見通し後退が主な要因とされる。ドル高により他通貨建てでの金購入コストが上昇し、投資需要を抑制したとみられる。一方、金は10月まで3カ月連続で月間上昇を維持しており、長期的な上昇基調はなお続いている。海外報道によると、各国中央銀行による備蓄需要やアジア諸国の実需が依然として価格を下支えしているという。特にインドや中国での買い意欲が堅調で、地政学的リスクやインフレ懸念を背景に安全資産としての魅力が継続している。市場関係者の間では、金価格は心理的節目である4,000ドル前後での攻防が続くとの見方が多く、今後の米金融政策やドル相場の動向が一段の方向性を左右するとみられている。
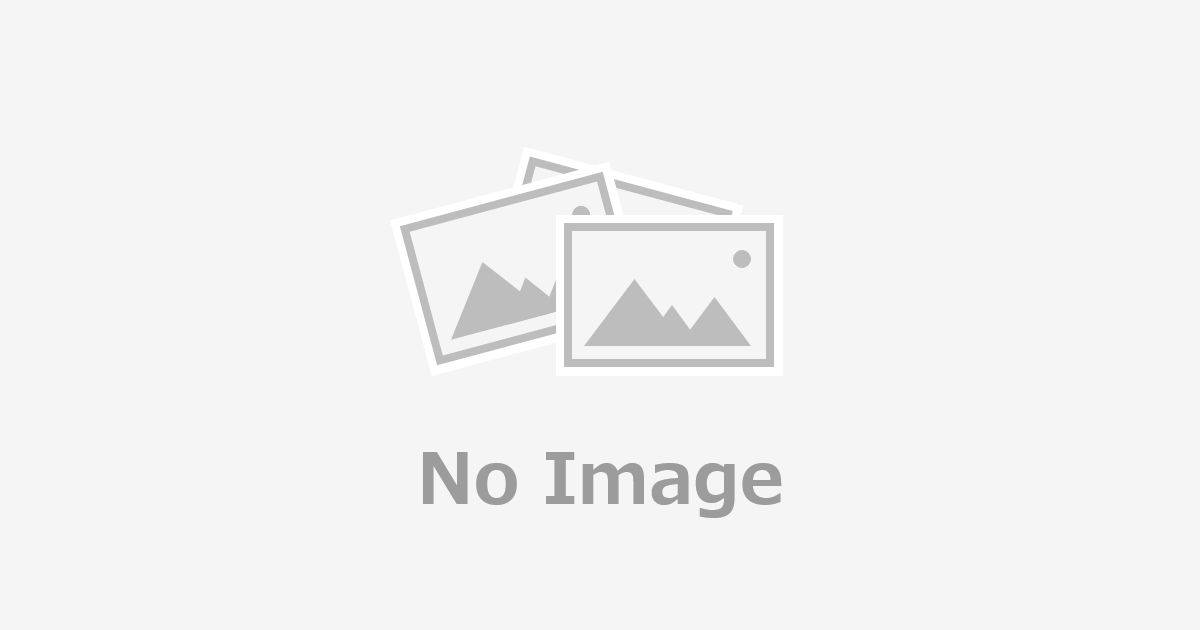
コメント Comments
コメント一覧
コメントはありません。
トラックバックURL
https://www.kinzoku.jp/blog/12431/trackback/