- 国内公表(買取価格1gあたり)
- 金 21,860円 (+572)
- プラチナ 8,711円 (+106)
- NY市場(終値ドル/トロイオンス)
- NY金 4,015.90ドル (+15.20)
- NYプラチナ ドル 1,614.30ドル (+13.50)
10/30、ニューヨーク市場の金は2日続伸。始値3,942.80ドル、高値4,041.50ドル、安値3,925.10ドル、終値4,015.90ドル、前日比+15.20(+0.38%)。米国のトランプ大統領と中国の習近平国家主席は、韓国・釜山で約6年ぶりに対面会談を行い、貿易や安全保障など幅広い分野で意見を交わした。海外主要メディアによると、両首脳は対立の激化を避け、協力の道を模索する姿勢を示したものの、根本的な対立点は依然として残された。ロイター通信などによれば、会談では米国が対中関税の一部を引き下げ、中国がレアアース(希少資源)の輸出規制を一時凍結することで合意。さらに中国は米国産大豆の輸入を再開する方針を示し、経済分野での一時的な緊張緩和が確認された。トランプ大統領は「アメージングな会談だった」と述べ、習主席も「協力は両国の利益にかなう」と応じたという。一方で、台湾問題や半導体輸出規制、中国の産業補助金政策といった構造的課題には具体的な進展が見られず、欧米メディアは「戦略的な休戦にすぎない」と指摘している。ガーディアン紙は「両国の根本的な不信感は解消されていない」と報じ、ポリティコ紙も「今回の合意は限定的で、履行の行方が焦点」と分析した。また、専門家の間では「今回の合意は市場の安定をもたらすが、地政学的な競争が終わったわけではない」との見方が強い。米中両国は今後も技術や安全保障の分野で覇権を競う可能性が高く、今回の会談は「対立を管理するための対話再開」と位置付けられる。米中関係は依然として試練の渦中にあるが、両首脳が直接会い、緊張緩和への糸口を探ったことは国際社会にとって前向きな一歩といえる。欧州中央銀行(ECB)は30日に開かれた理事会で、主要政策金利を3会合連続で据え置くことを決定した。預金ファシリティ金利を年率2.00%、主要リファイナンス金利を2.50%、限界貸出金利を2.75%とし、いずれも現行水準を維持した。海外主要メディアは、ECBが「現状の金融政策スタンスは良好な位置にある」として、成長とインフレの均衡を慎重に見極めようとする姿勢を評価している。ロイター通信は、ユーロ圏の物価上昇率が9月時点で2.2%と、目標の2%に近づいている一方、成長率は第3四半期に前期比0.2%増にとどまるなど、景気減速の兆しが残ると指摘。こうした中でECBが政策変更を急がず様子見を選んだのは妥当との見方を伝えた。ガーディアン紙も「インフレ懸念がくすぶる中での慎重な判断」とし、金融市場がほぼ織り込んでいたためユーロ相場や国債市場への影響は限定的だったと報じた。ラガルド総裁は記者会見で、「政策は今のところ良い位置にあるが、固定的なものではない」と述べ、データ次第で方針を見直す可能性を示唆。インフレ見通しや賃金動向、信用環境などを注視するとした。市場では、ECBが次の一手に関する明確な手掛かりを与えなかったことから、「慎重さを維持しつつも不透明感が残る」との声も上がる。報道各社は総じて、ECBがインフレ抑制と景気維持の微妙なバランスを取り続ける「中立的かつ忍耐的」な政策運営を続けるとの見方で一致している。ユーロ圏経済は貿易摩擦や地政学リスクといった外部要因の影響を受けやすく、次回12月会合で示される新たな経済見通しが、今後の政策方向を占う焦点となりそうだ。ニューヨーク・債券市場では米国債が売られ米長期金利が4.09%台まで上昇し、利息や配当を生まない資産である金の重荷となった。外国為替市場でユーロは対ドルで下落。金利差の拡大も意識されドル買い優勢となり、ドル建てで売買される金は割高感が高まった。海外金相場は上昇基調を維持し、1トロイオンス=約4,000ドル前後で推移した。米連邦準備制度理事会(FRB)が今週の米連邦公開市場委員会(FOMC)で政策金利を0.25%引き下げたことを受け、米ドルが弱含んだことが主な支援要因となった。海外報道では「金利低下により金の保有コストが相対的に下がり、安全資産としての魅力が増した」との分析が多い。さらに、トランプ米大統領と中国の習近平国家主席による会談を控え、市場の不確実性が意識されたことも金買いを後押しした。一方で、一部報道は「金価格は今月中旬の高値4,300ドル付近から5%超下落しており、調整局面にある」と指摘。米中関係の改善期待が強まれば、リスク選好回復による上値抑制もあり得るとの見方が示された。全体として、市場は「高値圏でのもみ合い」と評価しており、今後の相場は米金利動向と地政学的リスクが鍵を握るとみられている。
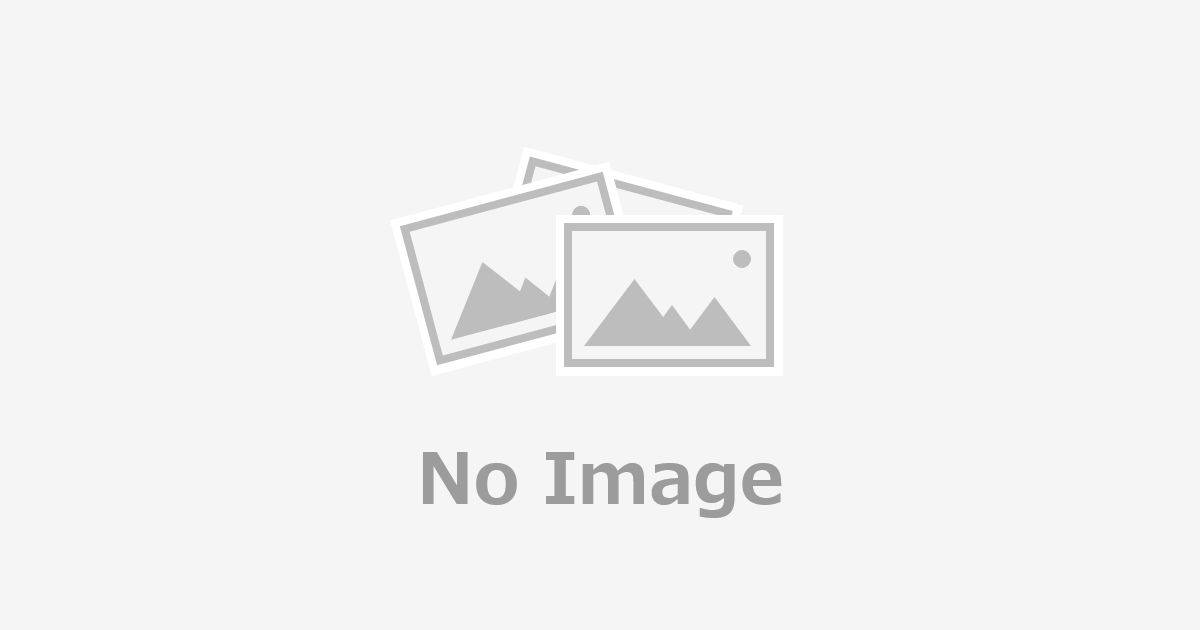
コメント Comments
コメント一覧
コメントはありません。
トラックバックURL
https://www.kinzoku.jp/blog/12429/trackback/