- 国内公表(買取価格1gあたり)
- 金 22,404円 (+144)
- プラチナ 8,846円 (+95)
- NY市場(終値ドル/トロイオンス)
- NY金 4,201.60ドル (+38.20)
- NYプラチナ ドル 1,687.90ドル (+11.40)
10/15、ニューヨーク市場の金は4日続伸で初の4,200ドル台。始値4,160.10ドル、高値4,235.80ドル、安値4,157.30ドル、終値4,201.60ドル、前日比+38.20(+0.92%)。米国モーゲージ銀行協会(MBA)が発表した10月10日終了週の住宅ローン申請指数は、総合指数が前週比-1.8%と小幅ながら2週連続の減少となった。住宅購入目的の申請を示す購入ローン指数は166.0(前週170.6)と低下し、借り換えローン指数も1168.0(前週1180.2)とわずかに減少した。一方、全体に占める借り換え比率は53.6%と前週の53.3%から上昇し、調整変動型ローン(ARM)の比率は9.3%(前週9.5%)にやや低下した。申請活動全体としては依然軟調であり、金利高止まりが需要を抑制している状況が続いている。特に購入ローンの減少は、住宅価格の高止まりや在庫不足に加え、長期金利上昇を背景としたローン金利の上昇が重荷となっていることを示唆する。借り換え需要は一部で続いているものの、金利低下局面には至っておらず、節約効果を狙った申請増加には限界が見られる。MBAは声明で「住宅ローン金利が依然として高水準にあり、消費者の購入意欲を抑えている」と指摘。今後の金利動向次第では、住宅市場の活動がさらに冷え込む可能性もある。総じて、今回の指数は住宅ローン需要の回復が遅れている現状を示す内容となった。10月の米ニューヨーク連銀製造業景気指数は、前月のマイナス8.7から大幅に上昇し、プラス10.7となった。市場予想のマイナス1.8を大きく上回り、製造業活動の改善を示す結果となった。新規受注や出荷の回復が指数押し上げの要因とみられ、企業の景況感に底入れの兆しが見られる。ただし、同指数は地域限定で変動が大きく、全米の製造業動向を直接示すものではないため注意が必要だ。専門家の間では「短期的な反発にとどまる可能性がある」との見方もあり、今後の持続性が焦点となる。米経済全体の製造業の方向性を見極めるには、ISM製造業指数や他地域連銀の指数との比較が重要とされる。今回の予想超えは市場にポジティブなサプライズを与え、ドル相場や株式市場に一時的な支援材料となった。一方、市場では米中貿易摩擦が再燃するとの懸念が高まっている。中国はレアアース輸出規制を強化し、米国は港湾使用料の応酬や関税引き上げを示唆。米通商代表部は規制拡大を通商合意違反と批判し、トランプ前大統領は中国製品への100%関税を示唆している。ただ、米中首脳会談や関税猶予の模索もあり、交渉余地は残る。為替市場ではドル安、金は上昇、原油や大豆は下落するなどリスクオフが進行。今後は関税発動や輸出規制内容、首脳会談の行方が焦点となる。ニューヨーク・債券市場では米国債が買われ米長期金利が4.02%台まで低下し、利息や配当を生まない資産である金の強みとなった。外国為替市場でユーロは対ドルで上昇し、ドル建てで売買される金は割安感が高まった。海外金相場は続伸し、NY市場のスポット価格は1トロイオンス=約4,200ドルと、過去最高水準に迫った。米連邦準備制度理事会(FRB)の年内利下げ観測が根強く、長期金利低下を背景に金利を生まない金への投資妙味が再び高まったことが主因とみられる。また、米中通商問題の不透明感や中東情勢の緊張が安全資産としての金需要を下支えした。加えて、中国や新興国中央銀行による金準備の積み増し姿勢も上昇要因となった。一方、過去最高値圏にあることから利益確定の動きも散見される。為替市場では円安・ドル高が進み、円建て金価格も1グラム当たり約20,100円台を維持。今後はFRB高官発言や米経済指標の結果を通じて、利下げ時期や金利見通しが金相場の方向性を左右するとみられる。また、米JPモルガン・チェースのジェイミー・ダイモンCEOは、ワシントンD.C.で開催されたフォーチュン誌主催の「モスト・パワフル・ウーマン」サミットに登壇し、現在の経済環境やリーダーシップについての見解を述べた。ダイモン氏は、金の保有について「現在のような環境ではポートフォリオに少し入れておくのが半ば合理的」と述べ、金価格が5,000ドルから1万ドルに達する可能性もあると指摘。ただし、金の保有には4%のコストがかかることから、積極的な買い手ではないとも語った。
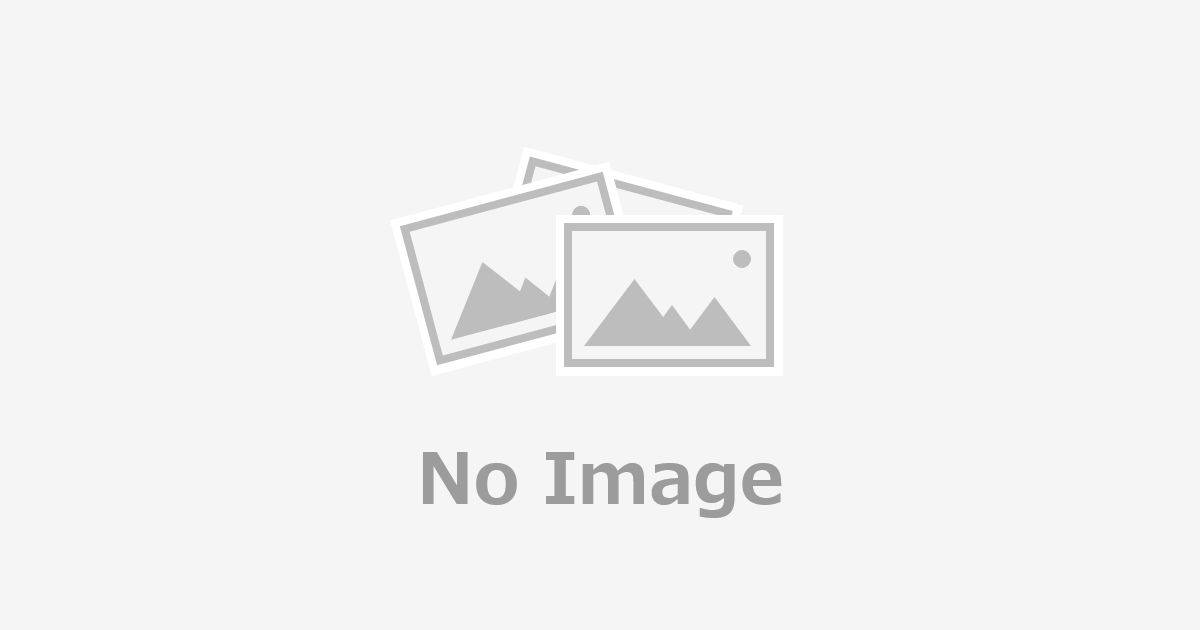
コメント Comments
コメント一覧
コメントはありません。
トラックバックURL
https://www.kinzoku.jp/blog/12378/trackback/